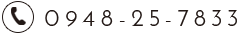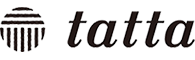- HOME>
- ブログ
お役立ち情報
車いすでも利用できるトイレを自宅に!バリアフリートイレ導入時の注意点
自宅にバリアフリートイレを施工
近年、バリアフリーやユニバーサルデザインなどの言葉が使われるようになって、街中ではエレベーターや多機能トイレなど、どのような人でも使うことができる施設が設置されてきました。 しかし、「自宅」のバリアフリー化については、十分ではないといえるでしょう。 それもそのはず、バリアフリー化が進められるようになり、一般化したのが2006年の法改正からであり、現在残っている住宅が建設された当初は、「バリアフリー」自体が先進的な考えであったからです。 しかし昨今、老後や不慮の事故による足腰の不自由に備えて、自宅をバリアフリー化する方も増えてきています。 自宅にバリアフリートイレを導入する際は、駅などの公共施設に設置されている多機能トイレほどの広さは必要ないので、建築面積上の問題で導入を諦めてしまうのはもったいないかもしれません。 この記事で、自宅にバリアフリートイレを設置するために最低限必要な面積を知り、検討してみてください。車いすでのトイレ利用は移乗方法を考えて
 車いすからトイレや浴槽など、様々なものに乗り換えることを移乗といいます。
一人で移乗ができる方から介助が必要な方まで、状態は様々であり、その状態によって、バリアフリー施設に必要な設備が異なります。
そのため、手すりやトイレ周りのスペースはどれぐらい必要か、転倒の心配はあるか等、身体の状態に合わせて設計することが必要です。
トイレの面積としては、180㎝四方の広さがあれば、車いすのままトイレに入って移乗することが可能であり、180㎝四方を確保することが難しければ、廊下など、トイレ外のスペースを利用することになります。
車いすからトイレや浴槽など、様々なものに乗り換えることを移乗といいます。
一人で移乗ができる方から介助が必要な方まで、状態は様々であり、その状態によって、バリアフリー施設に必要な設備が異なります。
そのため、手すりやトイレ周りのスペースはどれぐらい必要か、転倒の心配はあるか等、身体の状態に合わせて設計することが必要です。
トイレの面積としては、180㎝四方の広さがあれば、車いすのままトイレに入って移乗することが可能であり、180㎝四方を確保することが難しければ、廊下など、トイレ外のスペースを利用することになります。
トイレにたどり着くための動線も重要
トイレだけがバリアフリー化されていても、トイレにたどり着くまでに障壁(バリア)があると、意味がありません。 トイレのドアの幅は最低85㎝の有効開口(開く部分の長さのこと)を確保しましょう。 また、身体が不自由な方にとって、開き戸は扱いにくいので、引き戸を設置するとよいです。 トイレを設置する位置は、トイレを利用する方が普段利用している部屋からなるべく近い場所にして、段差をなくし、手すりをつけるとよいでしょう。 一口に「バリアフリー」といっても、身体の状態によって求められる機能が異なります。 身体の状態に合わせて必要な機能はどのような機能か、ケースワーカーなども利用して考えることで、本当に使いやすいトイレを設置することができるでしょう。バリアフリートイレ製品も利用
うまく利用することで、介助者と被介助者の両者の負担を軽減することができる製品も、メーカーから提供されています。 例えば、ベッドサイド水洗トイレは、ベッドの横に設置することができるので、寝ている間にトイレに行きたくなった時に重宝します。 また、車いすと便座の高さを合わせる補高便座や、トイレからの立ち上がりを補助するトイレリフトなども、身体の状態に合わせてうまく使うことで、トイレの負担が減るでしょう。 自分でできることが増えることで、被介助者の自信や自立にもつながり、心にも余裕がでてきます。 介助者や非介助者の心身の健康のためにも、道具をうまく使い、環境を整えることは大切なことなのです。バリアフリー住宅は注文住宅で実現
 建売住宅やマンションでは、バリアフリーを考えた設計になっていないことが多いです。
また、本来、「バリアフリー」は身体の状態に合わせて考える必要があり、一人ひとり必要な機能は異なります。
そこで、住みやすいバリアフリー住宅の建築を考えるのであれば、注文住宅が適しているといえるのです。
あなたの必要な機能や要望など、丁寧にヒアリングを重ねて作る住宅は、快適な暮らしを実現することでしょう。
理想の家を建てるためには、信頼できる建築会社を見つけることが大切です。
tattaでは、直接話し合いをしながら家づくりを進めることができるため、家づくりに関する様々な相談対応も可能です。
ぜひお気軽にご相談ください!
建売住宅やマンションでは、バリアフリーを考えた設計になっていないことが多いです。
また、本来、「バリアフリー」は身体の状態に合わせて考える必要があり、一人ひとり必要な機能は異なります。
そこで、住みやすいバリアフリー住宅の建築を考えるのであれば、注文住宅が適しているといえるのです。
あなたの必要な機能や要望など、丁寧にヒアリングを重ねて作る住宅は、快適な暮らしを実現することでしょう。
理想の家を建てるためには、信頼できる建築会社を見つけることが大切です。
tattaでは、直接話し合いをしながら家づくりを進めることができるため、家づくりに関する様々な相談対応も可能です。
ぜひお気軽にご相談ください!