BLOG
ブログ地震に強い家を建てたい人へ|福岡で注文住宅を建てるなら知っておくべき耐震の基本
福岡で注文住宅を建てるなら、おしゃれなデザインやこだわりの間取りはもちろん大切です。
しかし、何よりも優先したいのは、家族が毎日安心して暮らせる「安全性」ではないでしょうか。
「福岡は地震が少ないから大丈夫」と思われがちですが、2005年の福岡県西方沖地震では大きな被害が出ました。
さらに、福岡市中心部を走る「警固断層」の存在など、決して油断はできないのが現状です。
この記事では、注文住宅の耐震性に関する専門知識がない方でも、安心して家づくりを進められるように、以下の点を分かりやすく解説します。
- 福岡県が抱える具体的な地震リスク
- 「耐震等級」など、知っておくべき耐震性の基本
- 耐震性以外の重要なチェックポイント
この記事を読めば、あなたの家族にとって本当に安全で、心から満足できる注文住宅を建てるための、確かな知識と判断基準が身につきます。
一生に一度の大きな買い物で後悔しないために、ぜひ最後までご覧ください。
なぜ今、福岡の注文住宅で「耐震性」が最重要なのか?

家は、家族の命と財産を守るための最も重要な場所です。
日々の暮らしの中で、地震への漠然とした不安を感じることなく、心からリラックスできる空間であるべきです。
しかし、日本に住む以上、地震のリスクを完全に避けることはできません。
これは福岡県も例外ではなく、過去の災害の教訓や、専門家が指摘する未来のリスクに真摯に向き合う必要があります。
次の章では、福岡県が実際にどのような地震リスクを抱えているのか、具体的なデータをもとに見ていきましょう。
忘れてはいけない福岡の地震リスク|警固断層と過去の災害
福岡県が抱える地震リスクは、決して他人事ではありません。
具体的なリスクを知ることで、なぜ注文住宅において高い耐震性が求められるのかが明確になります。
- 警固(けご)断層
- 福岡市中心部を縦断する約34kmの活断層。M7.0程度の地震が発生した場合、市中心部で震度6強以上の揺れが想定されます。
- 市街地での建物の倒壊、火災、ライフラインの寸断など、深刻な都市機能麻痺のリスクがあります。
- 日向灘沖地震の影響
- 南海トラフ地震の一部として懸念される地震。発生した場合、福岡県でも長周期地震動による大きな揺れが予想されます。
- 特に高層マンションやビルがゆっくりと大きく揺れ続け、家具の転倒やエレベーターの停止といった被害が想定されます。
- 過去の地震災害
- 2005年 福岡県西方沖地震(M7.0)
最大震度6弱を観測し、死者1名、負傷者1,000名以上、住宅の全半壊は450棟を超える大きな被害が発生しました。 - 2016年 熊本地震
福岡県南部の大牟田市などで震度5強を観測し、家屋への被害も報告されました。「福岡は安全」というイメージを覆す出来事であり、活断層が活動する現実的な脅威を示しています。
- 2005年 福岡県西方沖地震(M7.0)
これらの事実から、福岡で家を建てる際には、国の定める最低限の基準を満たすだけでなく、万が一の大地震でも家族の命を守り、住み続けられるレベルの高い耐震性を確保することが極めて重要だといえます。
これだけは知っておきたい!耐震性の基本知識

「耐震性が大事なのは分かったけど、専門用語が多くて難しい…」と感じる方も多いでしょう。
しかし、基本的なポイントさえ押さえれば、ハウスメーカーや工務店の担当者の話を正しく理解し、適切な判断ができるようになります。
ここでは、「耐震・制震・免震」という3つの構造の違いと、性能を客観的に示す最重要指標「耐震等級」について、分かりやすく解説します。
①「耐震・制震・免震」3つの違いとコスト感
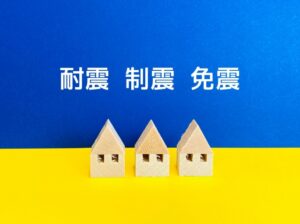
地震対策の構造には大きく分けて3つの考え方があります。
それぞれにメリット・デメリット、そしてコストが異なるため、ご自身の予算や求める安心のレベルに合わせて理解しておくことが大切です。
- 耐震(揺れに「耐える」)
- 仕組み
- 柱や梁、壁を強化し、建物自体を頑丈にして地震の力に対抗する。
- メリット
- 最もコストが安い
- 多くの会社で標準採用
- 設計の自由度が高い
- デメリット
- 繰り返しの揺れでダメージが蓄積しやすい
- 建物の上階ほど揺れが大きい
- 家具の転倒は防げない
- コスト目安
- 0円〜(建築基準法の基本)
- おすすめ
- コストを最優先に考えたい人。
- 仕組み
- 制震(揺れを「吸収する)
- 仕組み
- 建物内にダンパー等の装置を設置し、地震のエネルギーを熱などに変換して揺れを小さくする。
- メリット
- 繰り返しの揺れに強い
- 建物の損傷を軽減できる
- 耐震と組み合わせやすい
- デメリット
- 耐震よりコストがかかる
- 小さな揺れには効果が薄い場合がある
- コスト目安
- 50万円〜100万円
- おすすめ
- コストと性能のバランスを取り、より高い安心感を求める人。
- 仕組み
- 免震(揺れを「伝えない」)
- 仕組み
- 建物と基礎の間に装置を入れ、地盤の揺れを直接建物に伝わりにくくする。
- メリット
- 最も揺れを感じにくい
- 建物や家具の被害を最小限に抑えられる
- 地震後もすぐに生活を再開しやすい
- デメリット
- コストが非常に高い
- 軟弱地盤など土地の条件が限られる
- メンテナンスが必須
- コスト目安
- 300万円〜500万円
- おすすめ
- 最高の安全性を求め、予算に十分な余裕がある人。
- 仕組み
福岡の注文住宅では、コストと性能のバランスから「耐震」構造を基本とし、そこに「制震」装置をプラスする方法が現実的で効果の高い選択肢として人気があります。
②最重要指標「耐震等級3」は必須?等級ごとの安心度の違い

耐震性能を客観的に示す最も分かりやすい指標が「耐震等級」です。
これは住宅性能表示制度に基づくもので、等級1〜3の3段階に分かれています。
- 等級1
建築基準法で定められた最低限の基準。震度6強〜7の地震で倒壊・崩壊はしないが、大規模な修繕が必要になる可能性がある。一般的な住宅が該当し、地震保険の割引はない。 - 等級2
等級1の1.25倍の地震力に耐えられる。地震後の避難所となる学校や病院と同等のレベル。長期優良住宅の認定基準に該当し、地震保険は30%割引。 - 等級3
等級1の1.5倍の地震力に耐えられる。災害時の救助活動の拠点となる消防署や警察署と同等のレベル。住宅性能表示制度における最高等級であり、地震保険は50%割引。
熊本地震では、震度7の揺れに2度見舞われた地域で、耐震等級3の住宅は倒壊・全壊がゼロだったという調査結果があります。
この事実からも、家族の命を守り、地震後も安心して住み続けるためには「耐震等級3」の取得が極めて有効であると言えます。
【注意!】「耐震等級3相当」との違い
一部の住宅会社が使う「相当」という言葉には注意が必要です。
これは、正式な認定機関の評価(構造計算)を受けていないが「同等の性能がある」と自社で判断しているケースを指します。
法的な根拠や客観的な証明がないため、必ず「許容応力度計算」という詳細な構造計算に基づいた耐震等級3であることを確認しましょう。
失敗しない会社選びの秘訣|耐震性+αで見るべき3つの視点

耐震性が高いというだけで、理想の家が完成するわけではありません。
その高い安全性をベースに、長く、快適に、そして満足して暮らしていくためには、他の要素とのバランスが不可欠です。
ここでは、耐震性と同じくらい重要となる「デザイン」「快適性」という2つの視点から、後悔しない会社選びのポイントを解説します。
① デザインの自由度と耐震性は両立できる?

「耐震性を高めると、壁が増えて間取りが不自由になるのでは?」という心配をされる方がいます。
確かに、単純に壁の量を増やすだけの設計では、開放的な空間は作りにくくなります。
しかし、技術力の高い会社であれば、耐震性とデザイン性は十分に両立可能です。
その鍵を握るのが「構造計算」と「工法」です。
- 許容応力度計算
柱一本一本、梁一本一本にかかる力を精密に計算することで、どこを補強すれば安全性を保てるかが明確になります。これにより、不要な柱や壁を減らし、大開口の窓や広々としたリビングといった開放的なデザインを実現できます。 - ハイブリッド工法
木造軸組工法の「設計自由度の高さ」と、パネル工法の「面で支える強さ」を組み合わせた工法です。耐震性を確保しながら、多様なデザインに対応できるメリットがあります。
耐震性を理由にデザインを諦める必要はありません。
あなたの理想の間取りを実現できる技術力があるかどうかを、施工事例などを見ながら見極めましょう。
② 見えない価値「断熱性・気密性」が暮らしと資産価値を変える

地震が来ても安全な家は、いわば「守りの性能」が高い家です。
それに対して、日々の暮らしの快適さや経済性を左右するのが「断熱性・気密性」という「攻めの性能」です。
この性能は目に見えませんが、住み始めてからの満足度に大きく影響します。
- 光熱費を大幅に削減できる(家計に優しい)
家の熱が外に逃げにくく、外の暑さや寒さが侵入しにくいため、冷暖房の効率が格段にアップします。 - 家中が快適な温度に保たれる(健康に良い)
リビングと廊下、トイレなどの温度差が少なくなり、冬場のヒートショックのリスクを軽減します。 - 建物の寿命が延びる(資産価値を守る)
壁の内部結露を防ぎ、カビやダニの発生を抑制。構造材の劣化を防ぎ、家を長持ちさせます。
例えば、私たち「tatta」では、国の2030年基準を大きく上回るUA値0.46以下、最高等級のHEAT20 G3グレードに対応する高い断熱性能を基準としています。
さらに、家の隙間の少なさを示すC値も0.31㎠/㎡という高いレベルを実現。
PM2.5や花粉を99.9%除去する第一種熱交換換気システムも標準採用しており、耐震性だけでなく、家族が健康で快適に暮らせる住環境そのものを提供することに力を入れています。
まとめ:家族の未来を守る「安心の家」を福岡で建てるために
今回は、福岡で耐震性の高い注文住宅を建てるために知っておくべき知識と、会社選びのポイントを解説しました。
漠然とした不安を解消し、心から納得できる家づくりを実現するためには、以下の3つのステップが重要です。
- 福岡の地震リスクを正しく理解する
警固断層の存在や過去の災害から、耐震対策の必要性を自分事として捉えましょう。 - 「耐震等級3」を家づくりの基準とする
建築基準法の1.5倍の強度を持つ最高等級が、家族の命と財産を守るための確かな指標となります。 - 耐震性+αの視点で会社を比較検討する
高い安全性を確保した上で、デザインの自由度や、断熱性・気密性といった日々の暮らしの快適さも考慮し、総合的に満足できる会社を選びましょう。
一生に一度の大きな買い物だからこそ、慎重に、そして確かな知識を持って進めることが成功の鍵です。
まずは、気になる数社の資料請求をしたり、モデルハウスや見学会に足を運んでみてはいかがでしょうか。
あなたの家族の未来を守る、本当に安心できる住まいづくりを心から応援しています。
tattaでは、直接話し合いをしながら家づくりを進めることができるため、家づくりに関する様々な相談対応も可能です。 ぜひお気軽にご相談ください!
